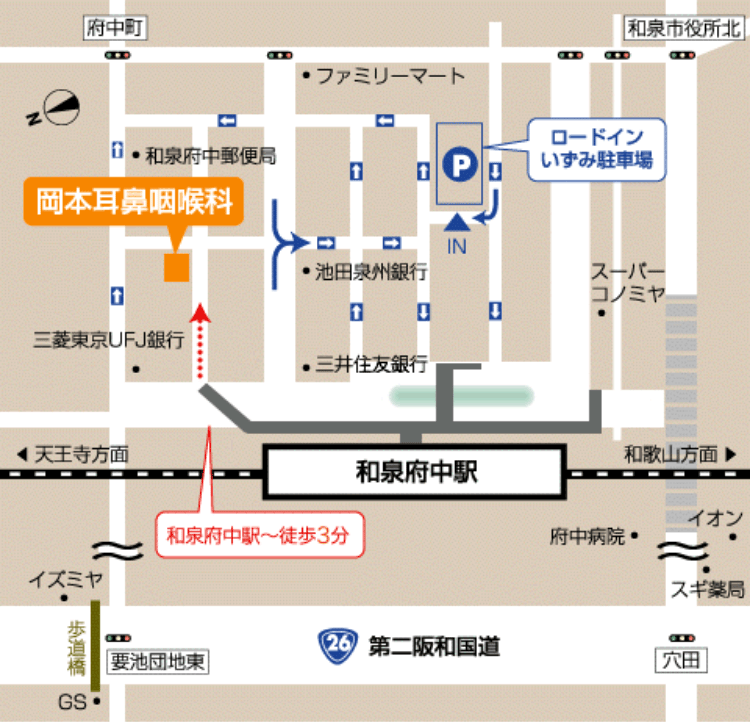のど・口について

のど(喉)と呼ばれる部分は、一般的には咽頭を指すことが多いです。ただし、耳鼻咽喉科の診療範囲としては咽頭だけではなく、口腔や喉頭、頸部などの部分も含まれます。なお、口腔や咽頭は消化管の始まりの部分でもあるため、食べ物を噛む、飲み込む、味覚を感じるなどの働きもあります。また、のどは鼻呼吸でも口呼吸でも空気の通り道になっているので、呼吸器としての役割も果たしています。このほかにも喉頭、咽頭、口蓋、舌などが動くことで、声帯を振動させ、音を出したり音程を変えたりといった働きもします。
これらの部位が何らかの原因によって異常を起こすと、上記の働きが正常に機能しなくなります。
よくみられる症状
以下の症状に心当たりがある方は一度当院をご受診ください。
- のどが痛い
- のどに異物感がある
- 物が飲み込みにくい
- 声のかすれや声がれが気になる
- 味覚がおかしい、感じにくい
- いびきが大きい
- 睡眠時無呼吸症候群を指摘された など
主なのど・口の病気
風邪
「鼻の症状」ページの「風邪」へ扁桃炎
咽頭炎の一つで、扁桃(主に口蓋扁桃)がウイルスや細菌に感染することで炎症が起きている状態を、扁桃炎(急性扁桃炎)といいます。扁桃の一部で、喉奥の左右両側に一つずつ存在する口蓋扁桃には、ウイルスや細菌が侵入してこないようにする役割があります。しかし、風邪や過労などによって、その機能が弱まると、それらに感染し、炎症を起こすのです。
主な症状として、強いのどの痛み、嚥下痛(唾を飲み込むだけで激痛が走る 等)、耳の痛みなどがみられます。また、患部には発赤や腫脹、白苔も確認できます。このほか全身症状として、発熱、全身の倦怠感、関節の痛みなども現れるようになります。
治療について
治療の内容は、症状の程度や原因によって異なります。例えば、ウイルス感染が原因であれば対症療法となり、消炎鎮痛薬(NSAIDs)や解熱剤を使用し、安静に過ごすようにします。また、細菌感染が原因であれば、抗菌薬を使用します。なお、扁桃炎を何度も繰り返す場合は、口蓋扁桃を切除する手術を行う必要があります。
喉頭炎
喉頭は、のど(咽頭)の奥に位置し、肺に向けて空気を送り込む気道の一部分でもあります。呼吸以外にも、発声や嚥下などの働きにも関わりがあるなど、かなり多機能な部位です。この喉頭の粘膜に炎症が起きている状態を喉頭炎と言います。
発症の原因は大きく急性と慢性に分けられます。急性喉頭炎は、風邪(ウイルス感染)の一症状で起こることが多く、声の出し過ぎによるのどの酷使、刺激物(喫煙、化学物質 等)の吸引、アレルギー反応が挙げられます。慢性喉頭炎は、急性喉頭炎を繰り返していることや、副鼻腔炎の後鼻漏による粘膜への刺激などによって発症するようになります。
主な症状は、のどの痛みや異物感、声がれ(嗄声)、物が飲み込みにくく感じるなどです。人によっては、発熱や全身の倦怠感がみられることもあります。
治療について
治療に関してですが、急性喉頭炎で痛みが強ければ、消炎鎮痛薬を使用します。また、原因が細菌感染であれば抗菌薬の投与、のどの酷使であれば声を出すのを控える、喫煙による刺激であれば禁煙をするなど、原因によって方法は変わっていきます。
上気道炎
鼻からのど(咽喉)にかけての急性炎症を総称して上気道炎といいます。炎症が発生する部位によって、急性鼻炎(鼻の粘膜)、急性咽頭炎(のど(咽頭)の粘膜やリンパ組織)、急性喉頭炎(のど(喉頭)の粘膜)などに細分化されます。
それぞれ単体で発症する場合もありますが、急性鼻炎と急性咽頭炎、急性咽頭炎と急性喉頭炎のように併発することや、急性鼻炎、急性咽頭炎、急性喉頭炎のすべてを同時に発症することもあります。
原因の多くは風邪ウイルスです。最初はウイルス感染だけでも、後から細菌感染が加わったり、もしくは最初から細菌感染が伴ったりすることもあります。
治療について
主に以下の治療を行います。
- 原因がウイルス感染のみと思われる場合は、鼻の炎症を抑える薬を処方します。
- 緑色っぽい鼻水が続き、細菌感染を起こしているときは抗生剤を処方します。
- ネブライザー治療(消炎剤などの吸入)
急性鼻炎と急性咽頭炎の症状は、2週間以上続くことはほとんどありません。急性鼻炎で2週間以上、緑色っぽい鼻水が続くような場合は、急性副鼻腔炎に罹っている可能性がありますので、早めに当院をご受診ください。また、急性喉頭炎は改善するまでに、通常1~3週間かかります。炎症がひどい場合は、1ヵ月程度かかることもあります。
声帯ポリープ
声帯は、声帯筋と粘膜上皮、粘膜固有層から構成され、発声の際の声帯振動に相応しい構造をしています。この声帯の粘膜に発生した腫瘤が声帯ポリープです。原因としては、声の酷使、上気道感染などによる炎症、喫煙などが挙げられます。これらによって粘膜から出血し、血腫などの形成が度々起こることでやがて腫瘤(ポリープ)となり発症します。なお、腫瘤はどちらか片側の声帯膜様部に現れます。
主な症状としては、ポリープによって声帯がしっかりと閉じることができなくなるため、声のかすれ(嗄声)やのどの違和感、乾燥、痰などがあります。
治療について
発症して間もなければ、声を出し過ぎないことや禁煙に努めるなどして様子を見ます。また、ステロイド薬の吸入や抗炎症薬を用いるなどの薬物療法を行うこともあります。これらの治療で改善効果がない場合には、声帯ポリープを切除するための外科治療となります。内容としては、全身麻酔による喉頭微細手術や局所麻酔下での喉頭内視鏡下手術があります。
喉頭がん
喉頭は気管の一部で、嚥下、発声、呼吸に関係する管状の器官です。喉ぼとけ付近に位置するこの部位に発生する悪性腫瘍のことを、喉頭がんといいます。発症の主な原因は喫煙とされており、60歳以上の喫煙者男性に多く見受けられます。主な症状は腫瘍の発生部位によって異なり、声門上部に発生するがんを声門上がん、声門部に発生するがんを声門がん、声門下部に発生するがんを声門下がんと診断します。
声門上がんの初期症状では、のどの違和感(のどのつかえ、のどに何かできている 等)、頸部リンパ節の腫脹などがみられるようになります。ただし、人によっては症状が軽度で、自覚症状がないこともあります。病状が進行すると、声がこもって聞こえる、耳の痛み、声がれ(嗄声)のほか、呼吸困難、血痰、喘鳴などが現れます。そのほか、リンパ節に転移しやすいという特徴もあります。
声門がんは、初期症状に声がれ(嗄声)がみられることが多いため、発症に気づきやすいのが特長です。また、喉頭がんの中では患者数が最も多いです。症状が進行すると、さらに声がれが悪化し、頸部のリンパ節に腫脹が確認できるようになります。このほか、呼吸困難、血痰、喘鳴などが現れます。
声門下がんは、上記2つのがんと比較すると、発生頻度はごくわずかです。初期の段階では無症状なことが多く、進行しやすいがんでもあります。進行すると、声がれ、頸部リンパ節の腫脹、吐く息に悪臭がみられるほか、呼吸困難、血痰、喘鳴などが起きることもあります。
治療について
治療の内容は、早期がんか進行がんかによって異なります。早期がんであれば、放射線治療、もしくは喉頭温存手術などの手術療法となります。進行がんでは、放射線治療と同時に化学療法(抗がん剤治療)を行う化学放射線治療や手術療法(咽頭全摘術 等)となります。
舌がん(口腔がん)
口の中(口腔内)で発生する悪性腫瘍を、総称して口腔がんと言います。発症部位によって、舌がん、口蓋がん、口腔底がん、歯肉がん、頬粘膜がんなどに分けられます。なかでも最も多いのが舌がんで、次に多いのが歯肉がんです。舌がんは口腔がん全体の6割程度を占めると言われています。
口腔がん全体でみられる主な症状としては、口腔内の痛み、腫れ、しこり、ただれ、出血、口内炎などがありますが、発症初期には自覚症状として現れにくいです。上記の症状が続いている場合は、一度当院をご受診ください。
発症の原因ですが、リスク要因として喫煙と飲酒が挙げられています。そのほか、口に合わない入れ歯の使用や虫歯の放置によって、慢性的に口内粘膜が刺激を受けていたり、口内が常に不衛生であったりすると発症リスクが上昇します。ちなみに、舌がんは50~60代の男性に発症しやすいがんと言われています。
検査は、がん病変が疑われる組織を一部採取し、顕微鏡で詳細を調べる組織診や、画像検査(レントゲン、CT、MRI 等)によって行います。治療では、基本的に手術療法によってがん細胞を切除していきます。また、進行がんのため切除が困難であると判断された場合は、化学療法(抗がん剤)と放射線療法を組み合わせた治療などが行われます。
味覚障害
味覚が弱まってきている(味覚減退)、味がよくわからない(味覚消失)、特定の味だけ感じることができない(解離性味覚障害)、本来の味とは異なる味を感じる(異味症)などの場合に、味覚障害と診断されます。
原因としてよく挙げられるのは、体内で亜鉛が不足しているケースです。味覚障害を訴える半数近くの方が、亜鉛不足によるものとされています。上記以外では、うつやストレスなどの心因性、薬剤(降圧薬、糖尿病薬、抗菌薬、抗うつ薬 等)の影響、新型コロナウイルス感染症に罹患した際の一症状などで現れるほか、原因不明の特発性という場合もあります。
治療に関して、亜鉛欠乏症による味覚障害であれば、体内で不足している亜鉛を補う亜鉛補充療法を行います。ただし、食事だけでは亜鉛不足を十分に補えないため、ノベルジン錠による薬物療法も用いられます。
また、何らかの病気が原因であれば、それに対する治療を行い、使用している薬物が原因であれば、薬の投与を控えるか、投与する量を減量するなどします。
口内炎
口の上顎(口蓋)や歯茎などの口内粘膜に発症した炎症が口内炎です。主な症状は口腔内の痛みや不快感です。あまりにも強い痛みがあると、摂食障害がみられることもあります。
同疾患は、原発性口内炎と症候性口内炎に分けられます。前者は、特定の原因で発症する口内炎のほか、原因不特定の口内炎も含みます。特定の原因には、栄養不足や睡眠不足、ストレスのほか、入れ歯が合わない、口内が不衛生、口内に何らかの外傷があるなどがあります。また、症状によってアフタ性(一部分で潰瘍のような炎症がみられる)とカタル性(粘膜に発赤や腫脹がみられる)に分けられます。
一方で症候性口内炎は、感染症や自己免疫疾患などの病気や薬剤の影響によって発症する口内炎です。感染症には、ウイルス(口唇ヘルペス、ヘルバンギーナ、麻疹、帯状疱疹 等)、細菌(梅毒、淋菌 等)、真菌(口腔カンジダ症 等)などが含まれます。自己免疫性としては、ベーチェット病、クローン病、全身性エリテマトーデス(SLE)などがあります。
治療について
治療方法は原因や症状によって異なります。原発性口内炎でアフタ性であれば、痛みを伴いますが、1~2週間程度で自然と治癒することが多いです。また、原発性で原因が特定されている場合は、その除去や治療を行います。治療ではステロイドを含む軟膏を使用します。症候性口内炎では、原因疾患の治療も行いますが、痛みなどの症状が強ければ対症療法も併せて行っていきます。