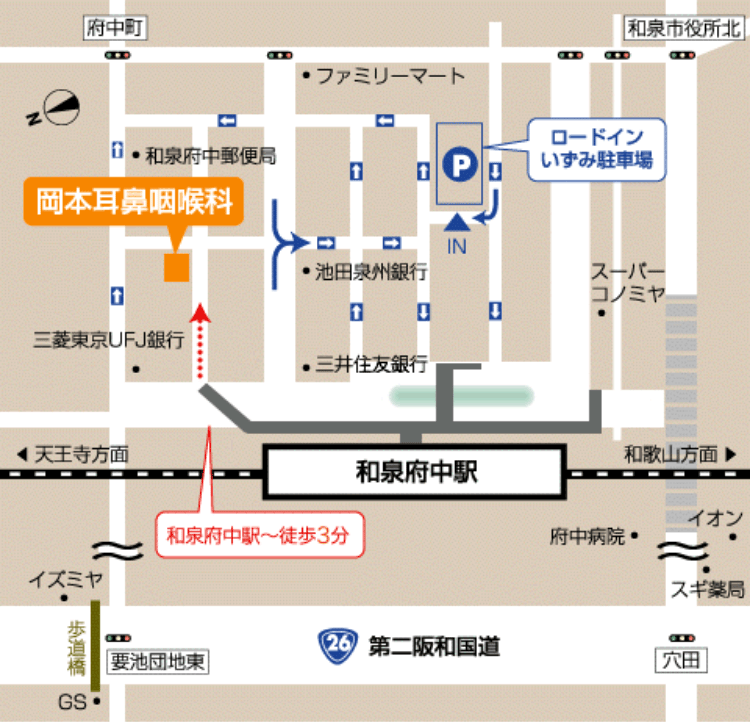睡眠時無呼吸症候群とは

睡眠時無呼吸症候群は、SAS(sleep apnea syndrome)といい、睡眠中に無呼吸状態が繰り返される状態のことです。具体的には、睡眠中に10秒以上呼吸が止まる無呼吸、または通常の換気量の半分以下になる低呼吸が、7時間の睡眠中に30回以上(1時間あたり5回以上)発生する状況を指します。
当院では、夜間無呼吸状態になっているかを調べる検査を行っています。検査機器を用いて自宅で検査(簡易検査、精密検査ともに)を行っていただけますので、ご興味のある方はご相談下さい。
症状について
睡眠時無呼吸症候群は、深刻な健康問題を引き起こすことがあります。主な症状として、日中の強い眠気や倦怠感、大きないびき、集中力の低下などが挙げられます。呼吸が止まることで、体が十分に休息を取れず、睡眠の質が著しく低下するためです。また、朝起きた時の頭痛や喉の乾き、頻尿、起床時の疲労感といった症状もよくみられます。この状態が長期間続くと、高血圧や心血管系の疾患、糖尿病などの合併症を引き起こすリスクが高まるため、早めの診断と治療が重要です。
睡眠時無呼吸症候群の種類
大きく2つに分類されます。1つ目は、閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)で、最も一般的なタイプです。これは気道が狭くなることで呼吸が一時的に止まるという状態で、肥満や扁桃肥大、鼻づまりなどが原因で起こります。2つ目は中枢性睡眠時無呼吸(CSA)です。これは脳が呼吸を制御する筋肉に適切な指示を出さないことが原因で、心不全や脳の疾患などが関連しています。
検査について
診断には、問診や簡易検査、睡眠ポリグラフ検査(PSG)が用いられます。問診では、いびきや日中の眠気の状況を正確に確認するため、家族やパートナーの協力を得ることも重要です。まずは簡易検査を行いますが、結果次第では精密検査に移行する場合があります。いずれの検査も自宅で行うことが可能であり、簡易検査は主に酸素濃度や呼吸状態を確認し、睡眠ポリグラフ検査(PSG)は、専門的な機器を用いて睡眠中の脳波、呼吸、心拍数、酸素濃度などを詳細に測定し、無呼吸の回数やその重症度を評価します。
治療について
治療方法は、症状の重さや原因によって異なります。軽度の場合、まずは肥満の改善やアルコール摂取の制限、規則正しい睡眠習慣の確立など、生活習慣の見直しが推奨されます。重度の場合には、鼻や口に装着したマスクを通じて気道に空気を送り込み、気道を広げるという持続陽圧呼吸療法(CPAP)が、最も一般的で効果的です。また、下顎を前方に固定する口腔内装置も、気道を確保する効果的な方法です。扁桃肥大や鼻づまりが原因の場合は、手術によって気道を広げることが考えられます。