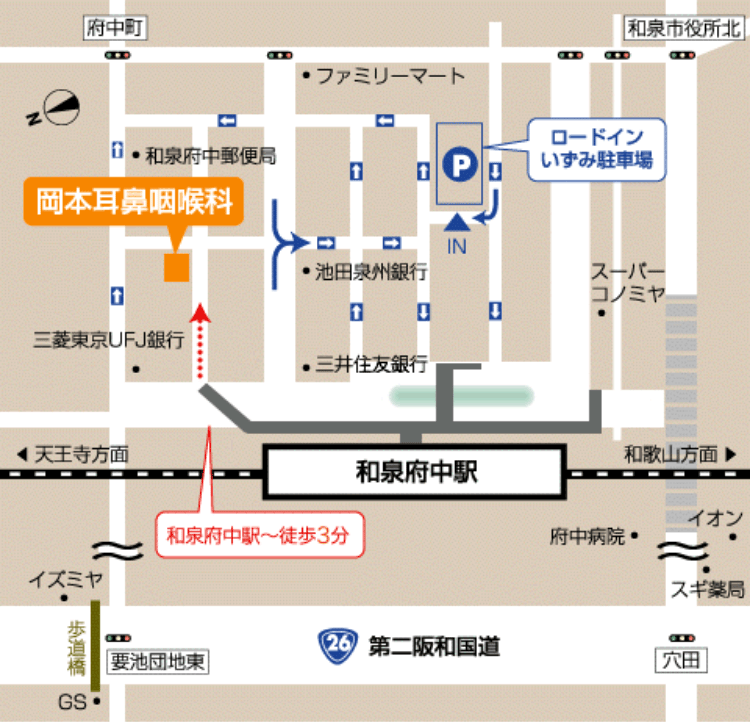鼻について

鼻は嗅覚としての働きはもちろん、呼吸器官としても大切な働きをしています。
嗅覚として働いているのは、鼻腔の真上、嗅上皮の奥にある嗅球で、ここで臭いに関する情報を電気信号に変換し、それを脳に伝えています。一方で、呼吸のための通路として働いている鼻の穴は、内側にある鼻毛でホコリや病原体などの侵入を防いでいます。また、その奥にある鼻腔は、吸入した空気の温度や湿度を調整する機能があります。呼吸は口でも可能ですが、のどなどには上記のような鼻にある機能がありません。そのため、ダイレクトに外気を吸い込むことになり、病気に罹患するリスクが高くなるのです。
よくみられる症状
鼻に関する以下の症状に心当たりのある方は、一度当院をご受診ください。
- 鼻が詰まって鼻呼吸ができない
- 鼻水
- くしゃみが止まらない
- 鼻血
- 臭いを感じない
- 鼻がくさい
- 鼻の周囲の腫れ、かゆみ
- 鼻を強く打つなどした
- いびきが大きい など
主な鼻の病気
風邪
風邪症候群、急性上気道炎とも呼ばれるもので、その8~9割程度が何らかのウイルス(アデノウイルス、RSウイルス、コロナウイルス 等200種類以上)に感染することで発症します。なお感染には、飛沫感染や接触感染などがあります。これによって、上気道(鼻、のど)や気管支などに炎症が起こり、鼻水・鼻づまり、咳、痰、のどの痛みのほか、発熱、頭痛、全身の倦怠感などの症状がみられます。
風邪には特効薬というものがありませんが、通常であれば1週間程度で自然と治癒するので、症状が深刻化しない限りは、医療機関に来院することは少ないかもしれません。ただし、風邪をこじらせると肺炎や気管支炎につながることもありますので、症状が強く出ているのであれば、早めにご受診ください。
治療について、軽度な症状であれば安静に努めていただきます。そのうち体内の免疫機能が働き出し、ウイルスが排出されていきます。また対症療法として、熱がある場合は解熱剤、鼻の症状(鼻づまり 等)が強い場合は抗ヒスタミン薬などを用いることがあります。
鼻炎
鼻炎は、鼻腔粘膜がなんらかの原因によって腫れてしまい、炎症が起きている状態です。これによって、鼻水が止まらない、鼻づまりが起きるなどの症状がみられるようになります。鼻炎を発症する疾患としては、風邪、アレルギー性鼻炎などが挙げられます。
アレルギー性鼻炎はこちら副鼻腔炎
「副鼻腔炎」のページへ鼻出血
一般的には鼻血と呼ばれます。鼻出血の原因は様々ですが、多くは鼻の穴をほじる、鼻をかむ、鼻を打撲するなどの外傷から、鼻粘膜の毛細血管が切れることによって出血するようになります。また鼻血だけでなく、くしゃみや鼻水の症状がある場合は、アレルギー性鼻炎、副鼻腔炎、鼻風邪などによって引き起こされていることが考えられます。
鼻出血の大半は、鼻の入り口付近で起きることがほとんどで、指などで圧迫することで止血できます。ただし、なかには動脈からの出血で、止血が困難なケースもあり、可能性としては非常にまれですが、脳疾患が原因の鼻出血ということもあります。
嗅覚障害
臭いの感覚が弱い、臭いを全く感じない、変な臭いがするなどの状態を嗅覚障害といいます。嗅覚障害は、量的異常と質的異常に分けられます。前者は臭いがしない状態で、後者は臭いが変だと感じる状態です。嗅覚障害の方の多くは、量的異常による嗅覚減退(臭いが弱い)、または嗅覚脱失(臭いを全く感じられない)です。
嗅覚障害は、原因によって大きく3つ(気導性嗅覚障害、嗅神経性嗅覚障害、中枢性嗅覚障害)に分けられています。気導性嗅覚障害は、鼻腔や副鼻腔などの疾患(副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎 等)によって嗅覚が障害を受けている状態です。この場合、原因疾患を治療することで、嗅覚の回復が見込めます。また嗅神経性嗅覚障害は、嗅細胞がダメージを受けている状態です。薬剤性嗅覚障害、ウイルス感染によって嗅粘膜が破壊されたことによる感冒後嗅覚障害、篩骨洞炎による慢性副鼻腔炎などが含まれます。中枢性嗅覚障害は、嗅球より上位から嗅覚中枢までの経路で障害が起きることで発生します。主に頭部外傷、脳腫瘍、アルツハイマーやパーキンソン病などの神経変性疾患によって引き起こされます。
治療に関してですが、原因疾患が判明していれば、それに対する治療を行います。なお、副鼻腔炎などの炎症性疾患による嗅覚障害の場合、ステロイド系の点鼻薬を使用することもあります。