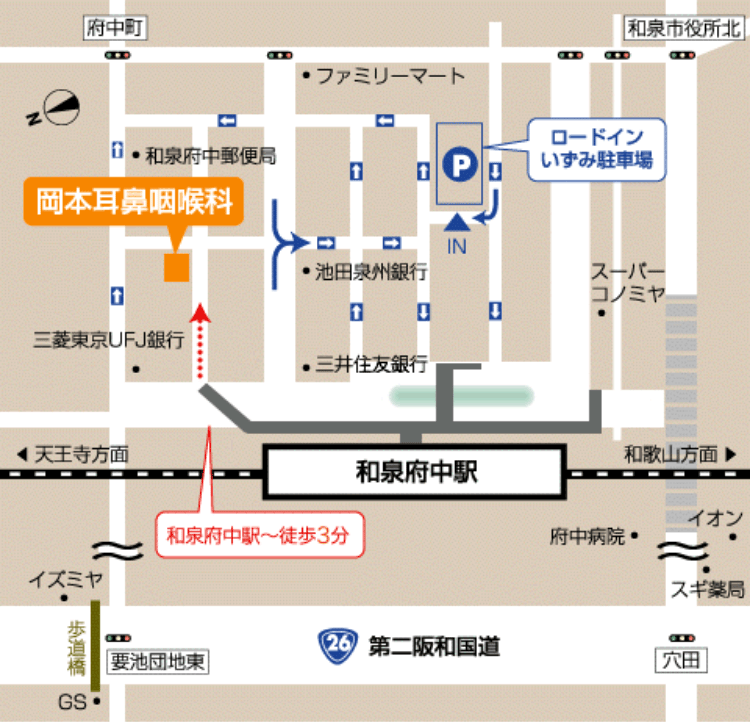難聴とは

音が聞こえない、あるいは音が聞こえにくいことにより、日常生活に支障をきたしている状態が難聴です。この場合、音として聞こえるまでの間(外耳や中耳から伝達してきた音を内耳で感知し、音を電気信号に変換して、蝸牛神経を通して脳に伝えられるという流れ)の部位で何らかの障害が起きている可能性が考えられます。難聴は障害を受けている部位に応じて、伝音難聴、感音難聴、混合性難聴の3つに分類されます。
伝音難聴
伝音難聴は、外耳から中耳の部位(外耳道、鼓膜、耳小骨 等)で発症し、音が小さく聞こえる状態です。一方で骨導聴力は正常であるため、自分の声を大きく感じてしまい、小声で話すようになります。難聴の度合は70dB(中等症)程度と言われ、原因疾患として、中耳炎(急性、滲出性、真珠腫性)、耳硬化症、外耳道狭窄(閉塞)、鼓膜穿孔などが挙げられます。特定の疾患以外では、耳垢や異物が外耳道に詰まることが原因で起こることもあります。
特定の疾患による場合は、その治療を行うほか、耳の洗浄、中耳に溜まった分泌液の除去などを行います。耳垢の詰まりが原因であれば、特殊な器具を使用して耳垢を除去します。
感音難聴
感音難聴は、内耳より中枢側の部位(蝸牛、聴神経 等)で障害が起きている状態で、音が小さく聞こえるだけでなく、歪んで聞こえるようにもなります。症状の程度は様々で、人によっては高度難聴や補聴器を使用していても聞き取れない重度難聴に罹ることもあります。この場合、気導聴力だけでなく骨導聴力の低下もみられます。なお、感音難聴は内耳で起きる内耳性感音難聴と、内耳より中枢側で起きる後迷路性感音難聴に分けられます。原因疾患としては、内耳性感音難聴は突発性難聴、騒音性難聴、加齢性難聴、メニエール病、薬物性難聴などが考えられます。後迷路性感音難聴では、聴神経腫瘍などの腫瘍性疾患、多発性硬化症などが挙げられ、特徴的な症状として、自分の声の大きさがわからず、大声で話すようになります。
治療について
突発性難聴などの急性難聴の場合は、放置していると聴力低下の状態が続くので、該当する症状があれば速やかにご相談ください。また加齢性難聴の場合は、加齢によって、音を感知する有毛細胞の数が減少することが原因なので、その状態を完全に改善することは困難です。そのため、補聴器を使用することで聞こえにくさを解消します。そのほか原因疾患がはっきりしている場合は、その治療を優先するようにします。
混合性難聴
伝音難聴と感音難聴が併発している状態です。原因疾患としては、耳硬化症の進行などが挙考えられます。それぞれの症状、原因に合わせて、治療方法を選択します。