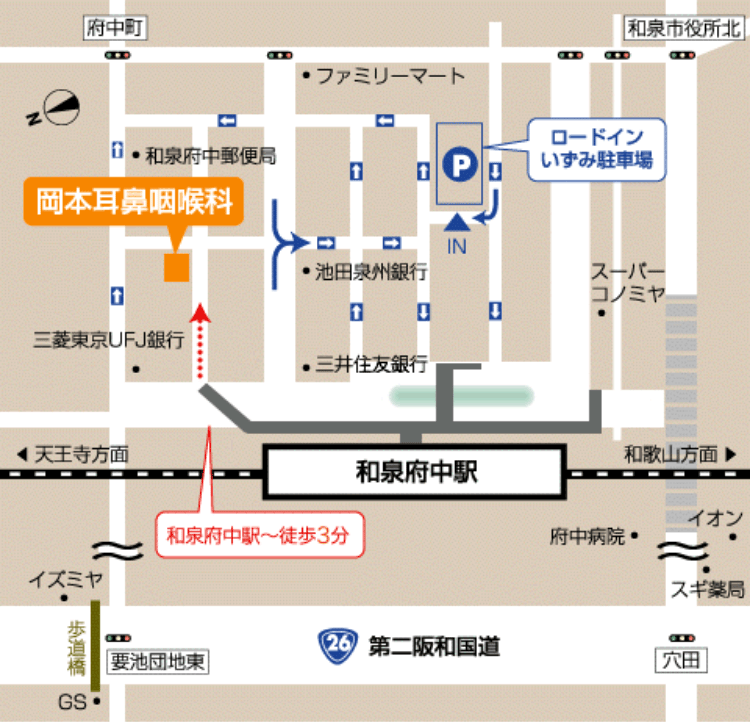小児耳鼻咽喉科とは

お子さまによくみられるとされている、耳、鼻、のどの病気を中心に診療します。特に小さなお子さまは、自らの言葉で症状を表現するのが困難です。はっきりとした原因がわからなくても、例えば、お子さまを呼んでいるのに気づかない、耳が気になるのかよく触っている、よく聞き間違えるなどの様子がみられる場合は何らかの耳の病気の可能性があります。また、鼻をしきりに触っている、鼻がいつも詰まっていて口呼吸をしている、鼻血がよく出るという場合は何らかの鼻の病気、いびきや声がれ(嗄声)、鼻呼吸が困難、嚥下が上手くできないという場合は、のどに何らかの疾患がある可能性があります。
上記のような症状がみられたり、耳、鼻、のどに関していつもと様子が違うと保護者の方が感じたりしたら、些細なことでも構いませんので一度ご受診ください。
耳・鼻・のどの病気が考えられる症状
以下のような症状がお子さまに見受けられたらご受診ください。
- テレビを観るときに音量を大きくしすぎる
- 聞き返しや聞き間違いが多い
- 呼んでも返事をしない
- 耳鳴りがするようだ
- 耳が塞がった感じがするようだ
- よく鼻水が出ている
- いつも鼻が詰まっている
- 鼻風邪を引きやすい
- 口をポカンと開けていることが多い
- よくのどを痛がり、発熱する
- のどがイガイガするようだ
- のどに異物感があるようだ など
小児によく見受けられる、耳・鼻・のどの病気
- 耳
- 中耳炎(急性中耳炎、滲出性中耳炎、慢性中耳炎、真珠腫性中耳炎)、内耳炎、外耳炎、耳介軟骨膜炎、外傷性鼓膜穿孔、耳垢栓塞、耳介血腫、耳管狭窄症、耳管開放症 など
- 鼻
- アレルギー性鼻炎、急性副鼻腔炎、慢性副鼻腔炎、花粉症、嗅覚障害、鼻中隔湾曲症 など
- のど
- 急性扁桃炎、慢性扁桃炎、口蓋扁桃肥大、アデノイド肥大、味覚障害、耳下腺炎、摂食・嚥下障害 など
中耳炎
「中耳炎」のページへ異物混入
お子さまは、なぜか小さなおもちゃなど手にしたものを鼻や耳に入れて遊びたがります。具体的には、ビー玉やスーパーボール、紙切れ、消しゴムなどで、特に3歳前後のお子さまに多いので注意が必要です。お子さまがなにか詰めてしまった場合に、無理に取ろうとすると、余計に奥に入り込み取れにくくなってしまうので、すぐに当院へご来院ください。
異物混入の疑いがあれば、ファイバースコープを用いて、異物が詰まっている部位を観察します。なお、検査時に鼻に異物が詰まっている場合、異物をのどの奥に落下させて飲み込まないように注意する必要があります。
処置方法
異物を詰めると、詰まった物や部位、状態によって、その処置方法は異なります。
例えば、目に異物が入った場合は、洗面器に張った水に顔をつける、目薬を使うなどして、異物を流します。また、混入したものが洗剤や薬品であれば、流水で目を洗うことで、一緒に流してしまいます。
鼻に詰まった異物は、詰まったものが外から見える場合は、指などで慎重に取り出し、見えない場合は、反対側の鼻の穴を刺激することでくしゃみを誘ったり、鼻をかませたりします。それでも取れない場合は、ピンセットなどで慎重に取り出します。
耳に異物が入った場合は、取り出せそうであれば、詰まっている方の耳を下にして、耳介を少し後ろに引っ張り、頭の反対側を軽くたたくなどします。なお、長いものが混入してしまった場合は、誤った取り出し方によって鼓膜を傷つける恐れがあるため、綿棒や耳かきなどで取り出そうとせず、すぐに耳鼻咽喉科を受診してください。
何かしらの異物が偶然入ってしまうことは避けられないことですが、お子さまが遊んでしまいそうなものは、できる限りお子さまの手の届かないところに置くようにしましょう。
扁桃肥大・アデノイド肥大
扁桃肥大
口蓋扁桃が肥大化している状態を指します。口蓋扁桃は3歳頃から大きくなり始め、7歳頃に最大化し、その後は成長するに従って小さくなっていきます。口蓋扁桃が大きくなると、いびきや睡眠時無呼吸症候群を引き起こすといった症状や、呼吸障害、食べ物を飲み込むのに時間がかかるなどの障害が起きるようになります。症状が軽度であれば自覚症状はほとんどみられませんが、上記のような症状がみられた場合は、一度当院へご相談ください。なお、症状が強く出ている場合は、口蓋扁桃の摘出手術を行うこともあります。
アデノイド肥大
鼻の奥の突き当たった部分にある上咽頭のリンパ組織の塊のことをアデノイドといいます。この塊は2歳頃から大きくなり始め、6歳頃に最大化していきます。その後は成長するに従って小さくなっていき、10歳を過ぎる頃には目立たなくなります。アデノイドが肥大化することで、主に口呼吸、鼻づまり、鼻声、いびきや睡眠時無呼吸症候群などの症状が現れます。肥大化したとしても症状がなければ経過観察となりますが、上記の症状によって呼吸障害や睡眠障害が起きている場合は、アデノイドを切除する手術療法を検討します。
小児副鼻腔炎
お子さまは身体の発達過程にあるため、耳鼻咽喉科領域でいうと、副鼻腔が未発達であったり、耳管が水平に寝ていて太かったりするという特徴があります(副鼻腔は10歳前後で大人と同じくらいに成長します)。
そのため、急性副鼻腔炎などを起こしやすい傾向があります。特に2歳以下のお子さまが繰り返しやすく、5~6歳になると減っていきます。
副鼻腔炎についてはこちら流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
一般的にはおたふくかぜと呼ばれており、主に3~6歳の幼児に発症しやすいといわれています。ムンプスウイルスが原因で、飛沫感染もしくは接触感染によって引き起こされます。感染後2~3週間の潜伏期間を経て発症することが多いです。
主な症状は、発熱、両側もしくは片側の耳下腺(耳の下の頬の部分)の腫脹、それに伴う痛みなどです。発症後、腫脹による症状の山場は48時間前後で、腫れ自体は1週間程度で治まっていきます。
合併症として、無菌性髄膜炎、膵炎、難聴などを併発することもあります。また、思春期以降におたふくかぜに罹患すると、女子は卵巣炎、男子は精巣炎を併発する可能性があります。
治療について
治療に関してですが、特効薬はなく、基本的に対症療法を行います。熱や痛みがある場合は、解熱鎮痛薬を使用し、安静にすることで症状を和らげていきます。なお感染予防のため、耳下腺の腫れが現れてから5日が経過し、かつ全身の症状が改善するまでは、登園・登校はできません。
ヘルパンギーナ
主にコクサッキーウイルスが原因とされており、飛沫感染もしくは接触感染によって引き起こされます。手足口病と同様に夏季に発症しやすく、乳幼児の患者さまが多いのが特徴です。2~4日の潜伏期間を経て、39度以上の発熱や、口腔内の後方に水疱やアフタが現れます。発熱は3日程度で治まりますが、水疱が破れて潰瘍化すると、のどに強い痛みがみられるようになります。のどに痛みを感じると、水分をとるのを嫌がるなどして脱水症状に陥ることもあるので要注意です。
治療についてですが、特効薬がないため、強い症状が出ている場合は対症療法を行います。熱や痛みに対しては解熱鎮痛薬を使用し、のどの痛みには刺激が少ない食事(軟らかい、味が薄い 等)を意識していただきます。そのほか、こまめに水分を取らせることも重要です。なお、水分や食事が十分に取れない場合は、点滴療法を行うこともあります。
手足口病
コクサッキーウイルス(A群)もしくはエンテロウイルスなどが原因の感染症で、ヘルパンギーナ同様、夏季に発症しやすく、乳幼児によくみられるのが特徴です。感染経路は、飛沫感染もしくは接触感染で、3~5日の潜伏期間を経て発症します。主な症状としては、手のひらと足の裏に小さな水疱、口腔内の前方に水疱が現れます。人によっては38度以下の発熱が出ることもあります。なお、手足の水疱には痛みやかゆみはみられませんが、口内の水疱については、破れることでただれや潰瘍となり、痛みを引き起こすこともあります。
これといった治療をせずとも、1週間程度で自然と治癒していきます。治療が必要な場合には、対症療法を行います。例えば、口の中の水疱に口内炎のような痛みがあれば、患部に軟膏を塗布するなどします。