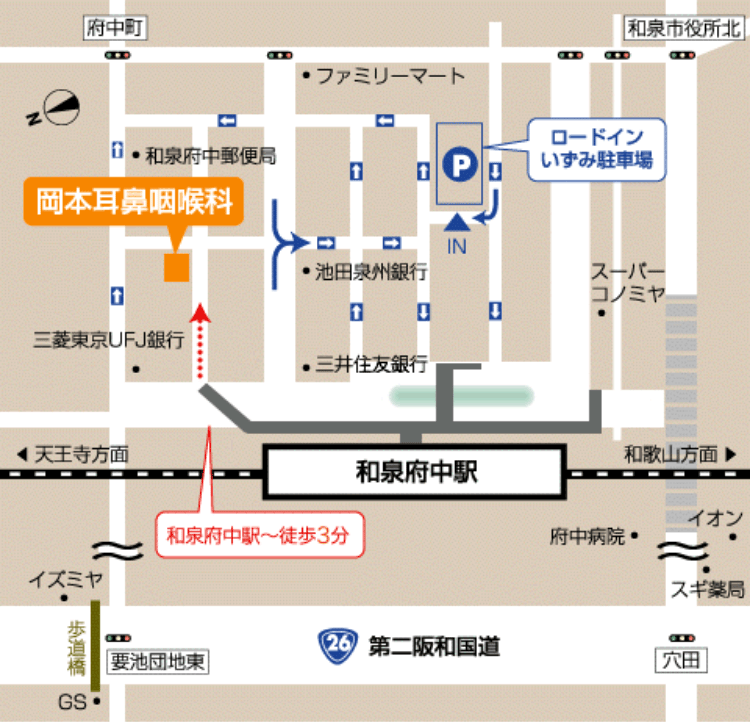唾液性疾患
唾石症
石(唾石)が唾液腺や導管の中に発生する病気です。唾石の大きさは、砂粒大のものから数センチあるものまで様々です。原因としては、唾液の停滞や唾液の性状の変化、導管の炎症といったことが考えられています。
症状としては、痛みを伴った顔の腫れや顎下の腫れが見られます。何かを食べようとする、もしくは食べている最中は激しい痛みを感じますが、時間の経過とともに共に症状は消えていきます。
治療について、小さな唾石であれば開口部からそのまま自然に流出することもあります。ただし、痛みを繰り返す場合は小手術が必要となります。また、唾石が導管内にある場合は、口の中で切開して唾石だけを摘出し、唾液腺の中にある場合は、腺体ごと唾石を摘出します。
唾液腺炎
唾液腺に炎症が起きた状態を指します。原因は様々ですが、多くはウイルスや細菌の感染によるものがほとんどです。なお、ウイルス感染で代表的なものが流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)です。唾液腺炎を発症すると、抗菌作用、消化作用、粘膜保護作用などの唾液本来の機能が低下し、症状としては炎症部分の腫れと痛み、口の中の乾燥、発熱、寒気、唾液の減少などがみられます。
治療について、ウイルス性のものであれば解熱薬を投与するほか、安静にして様子を見ます。また、細菌による感染症の場合は抗菌薬を使用します。
唾液腺腫瘍
唾液腺に発生する腫瘍です。多くは耳下腺でみられますが、顎下腺や小唾液腺などでもみられます。小唾液腺や舌下腺に腫瘍が発生すると、口腔内で症状が現れます。なお、唾液腺腫瘍は良性の場合が多いですが、舌下腺に発生した場合は悪性の腫瘍であることが多いです。
主な症状は、耳や頬、顎付近や口の中のしこりです。また、食べ物を飲み込みにくくなったり、口を大きく開けにくくなったりします。そのほかにも、顔の感覚や顔の筋肉の麻痺(顔面神経麻痺)、顔の痛みなどが起こることもあります。
治療では、手術により腫瘍を摘出します。場合によっては、放射線治療や化学療法を併用することもあります。
リンパ腺腫脹
頸部のリンパ節が炎症や腫瘍を起こしている状態をリンパ節腫脹といいます。その中でもよく見られる炎症が、ウイルスや細菌の感染によって炎症を引き起こされる急性リンパ節炎と、急性リンパ節炎が治癒しないまま長引いた状態の慢性リンパ節炎です。
急性リンパ節炎は、リンパ節腫脹の中でも発生頻度が高く、腫れた部位を押したり、首を曲げたりしたときに痛みを感じます。小児によく見られ、扁桃炎や虫歯の炎症をきっかけに、細菌がリンパ節に入ることで発症します。また、成人の場合は、糖尿病の合併症である癰(よう)や癤(せつ)といった皮膚感染症が出ている場合に起こります。これらは結核性リンパ節炎も含め、原因となる病気の治療にあたることで、リンパ節の痛みや腫れを抑えます。ただし症状がひどければ、抗菌薬や消炎鎮痛薬を使用します。これらの治療により、症状はおよそ1~2週間ほどで改善していきます。
なお、首のリンパ節に腫瘍ができる場合の多くは悪性です。腫瘍が確認されたら、すぐに他の部位へ転移しているかを検査し、その後に抗がん剤などの治療を行います。また、のど、食道、甲状腺など他の部位から首にがんが転移することもあります。その場合は、元のがんと転移リンパ節の両方を治療する必要があります。
顔面神経麻痺
顔面神経とは顔面を動かす神経のことで、同神経が障害を受けると表情筋を動かせなくなるのですが、これを顔面神経麻痺といいます。顔面神経麻痺が起こると、顔が左右非対称に見える、口やまぶたが閉じられない、額のしわを寄せることができないといった症状や、味覚障害、涙液・唾液の分泌低下などを伴うこともあります。
顔面神経麻痺の多くは、原因が特定できないベル麻痺です。これは顔面神経管内の顔面神経が水膨れ状態となり、顔面神経麻痺を引き起こすものです。ほかには、耳介や外耳道に現れた水泡により痛みを伴うラムゼイ・ハント症候群があり、これは顔面神経がウイルスに感染することが原因となります。また、慢性中耳炎(特に真珠腫性中耳炎)により、中耳内にある顔面神経が損傷し、顔面神経麻痺が引き起こされることもあります。
治療に関してですが、脳梗塞など原因が特定されていれば、その病気の治療を行います。ベル麻痺のように原因不明の場合は、ステロイド薬の使用、ビタミンB12の内服などの薬物療法などが行われます。