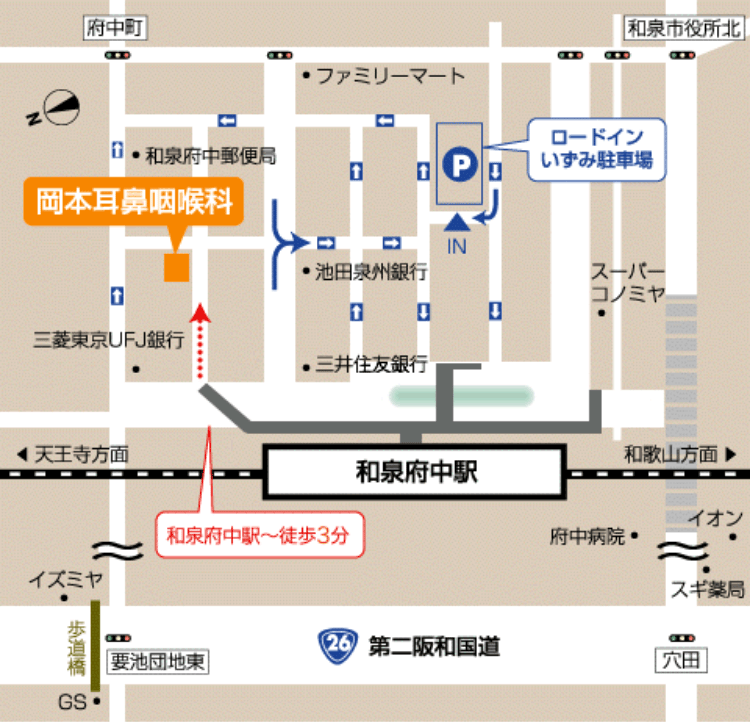耳について

耳は大きく外耳、中耳、内耳の3つの部位に分けられます。耳介から鼓膜の手前までの部分を外耳、鼓膜、鼓室、耳管の部分を中耳と言い、どちらも内耳に音を伝達させる働きがあります。内耳は、鼓室よりもさらに奥側の部分で、半規管、蝸牛、前庭などが含まれます。音が外耳道から奥へ伝わると、鼓膜や耳小骨が振動し、それが内耳のリンパ液まで振動させると音を感知するという仕組みです。また、内耳は平衡感覚、いわゆる体の傾きや回転を司る器官でもあります。
これらに異常が生じたり、病気に罹ったりすると、耳が聞こえにくい、めまいがする、耳が痛い、耳が詰まったような感覚があるなどの症状が起きるようになります。
よくみられる症状
- 耳が痛い
- 耳がかゆい
- 耳だれ(耳漏)
- 耳が臭い
- 音が聞こえにくい
- 耳の中が詰まっている(耳閉塞感)
- 耳鳴りがする
- めまい、ふらつきがある など
主な耳の病気
中耳炎
「中耳炎」のページへ外耳炎
外耳道炎とも呼ばれます。外耳道とは、耳の穴の入り口から鼓膜の手前までの部分のことです。この部分に傷がつくと、細菌(黄色ブドウ球菌 等)や真菌(カンジダ 等)に感染し、炎症が起きてしまいます。これを外耳炎といいます。耳かきや爪で外耳道を引っ掻いたり、海水浴やプールに行ったりした後に発症しやすくなります。主な症状として、耳の痛みやかゆみのほか、膿を伴う耳だれ(耳漏)がみられることもあります。なお、外耳道の入り口3分の1程度に発症する外耳炎を限局性外耳道炎、3分の1より内側で起きる外耳炎をびまん性外耳道炎と言います。
治療では、抗菌薬の点耳薬や軟膏を使用します。また、かゆみの症状が強ければ、抗ヒスタミン薬を使用することもあります。このほか強い痛みや耳せつ(耳のおでき)がある場合は、切開や排膿を行います。
耳垢栓塞
耳垢栓塞(じこうせんそく)は、一般的には耳あかと呼ばれています。そもそも耳あかとは、外耳道の中にある皮脂腺や耳垢腺からの分泌物と表皮や埃などが混在したものです。この耳あかは、耳垢腺からの分泌量によって、ドライかウェットの2種類に分けられます。分泌量が少なければパサパサのドライ(乾性耳垢)に、多ければネトネトした飴状のウェット(湿性耳垢)になるとされ、日本人はドライが多いと言われています。
耳垢塞栓とは、耳あかが外耳道で詰まることで閉塞した状況となり、それによって耳が詰まる、こもるといった症状が現れる状態です。耳あかが乾性耳垢(ドライ)であれば、自然と排出されることが多いのですが、湿性耳垢(ウェット)の場合、耳あかが外耳道内で付着した後、そのまま固まってしまい詰まりやすくなります。きっかけとしては、綿棒や耳かきで耳あかを取っていたつもりがさらに奥へ押し込んでしまった、シャワーや水泳などで外耳道に水が入り、耳あかが膨張してしまったということが挙げられます。急に音が聞こえなくなったという患者さまが、この耳垢塞栓だったということも少なくありません。
耳垢を除去することで治療しますが、外耳道であまりにも固くなっている場合は、耳垢を溶かす液体を使用し、耳垢鉗子や吸引管によって除去していきます。
難聴
「難聴」のページへ耳鳴り
耳鳴りは耳鳴(じめい)とも呼ばれるもので、実際に音は出ていないにもかかわらず、自分の耳の中で音が鳴っているような感覚のことを指します。耳鳴は大きく2つに分類され、他人は聞くことができない本人にしか聞こえない音を自覚的耳鳴、他人にも聞こえる音を他覚的耳鳴といいます。なお、耳鳴りを訴える患者さまの多くは自覚的耳鳴です。また、耳鳴りを訴える方の9割以上は、何かしらの難聴がみられるとされ、難聴の原因を突き止めることで耳鳴りが改善されるということが少なくありません。
耳鳴りを訴える患者さまに聞こえる音は、「ジー」「ピー」「ザー」「ゴー」「キーン」「ガンガン」「ザッザッ」など様々で、高音の耳鳴りもあれば、低音の耳鳴りもあります。これらの音の種類や耳鳴りが起こっているのが片側か両側かなどによって、原因疾患が判明することもあります。
このような症状がある場合、耳から脳にかけての聴覚経路(外耳、中耳、内耳、聴神経、中枢神経など)で異常が起きたと考えられることが多いですが、人によってはストレスなどによる心因性で起こることもあれば、全身性疾患が原因となることもあります。
なお自覚的耳鳴の場合は、内耳から蝸牛神経節の間で何らかの障害があることで耳鳴りが発生する末梢性と、蝸牛神経節より中枢側に何らかの障害があることで耳鳴りが発生する中枢性に分けられます。末梢性では、原因疾患として突発性難聴、加齢性難聴、騒音性難聴、中耳炎、外耳道炎、メニエール病、薬物性難聴などが挙げられます。中枢性の場合は、高血圧や聴神経腫瘍などの腫瘍性の疾患が原因として考えられます。
治療について
原因疾患がはっきりしている耳鳴りに関しては、その病気に対する治療を行います。一方で、原因が特定されていない耳鳴り、あるいは加齢性難聴の場合は、薬物療法として、ビタミンB12や血流改善薬などを使用し、医師が必要と判断すれば、漢方薬などを用いることもあります。
耳管狭窄症
耳管が常に閉塞している状態で、物を飲み込むなどの嚥下やあくびをしても閉じたままの状態になっています。乳幼児と高齢者に起こりやすい症状であるといわれています。
発症の原因は、病気や老化現象によるものとされ、病気の場合は風邪などの急性上気道炎による耳管の炎症、鼻炎や副鼻腔炎、アデノイド増殖症、上咽頭腫瘍などが挙げられます。このほか急激な気圧変化、口蓋裂や頭蓋骨格が未成熟であること、加齢などによって引き起こされることもあります。なお、耳管狭窄症を放置すると、滲出性中耳炎を発症することもあるので、異常に気づいたら早急に当院をご受診ください。
耳管狭窄症でよくみられる症状は、耳が詰まっている感じ(耳閉塞感)、自分の話し声が聞こえにくい、自分の声が重なって聞こえる、自分の呼吸音が聞こえるなどです。
患者さまの症状や訴えなどから耳管狭窄症が疑われる場合、聴力検査や中耳内の空気圧を調べるティンパノメトリーなどを行い、中耳の状態や聴こえ具合などを確認します。
治療について
原因疾患が明確な場合は、疾患に対する治療が行われます。なお、症状が改善しない場合は、耳管通気(鼻に細い管を入れ、鼻咽腔から中耳に空気を送り込むことで、塞がった耳管を広げる方法)などを行います。